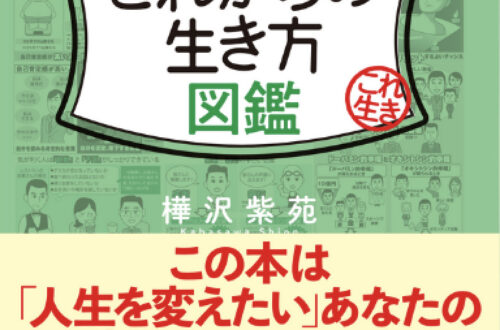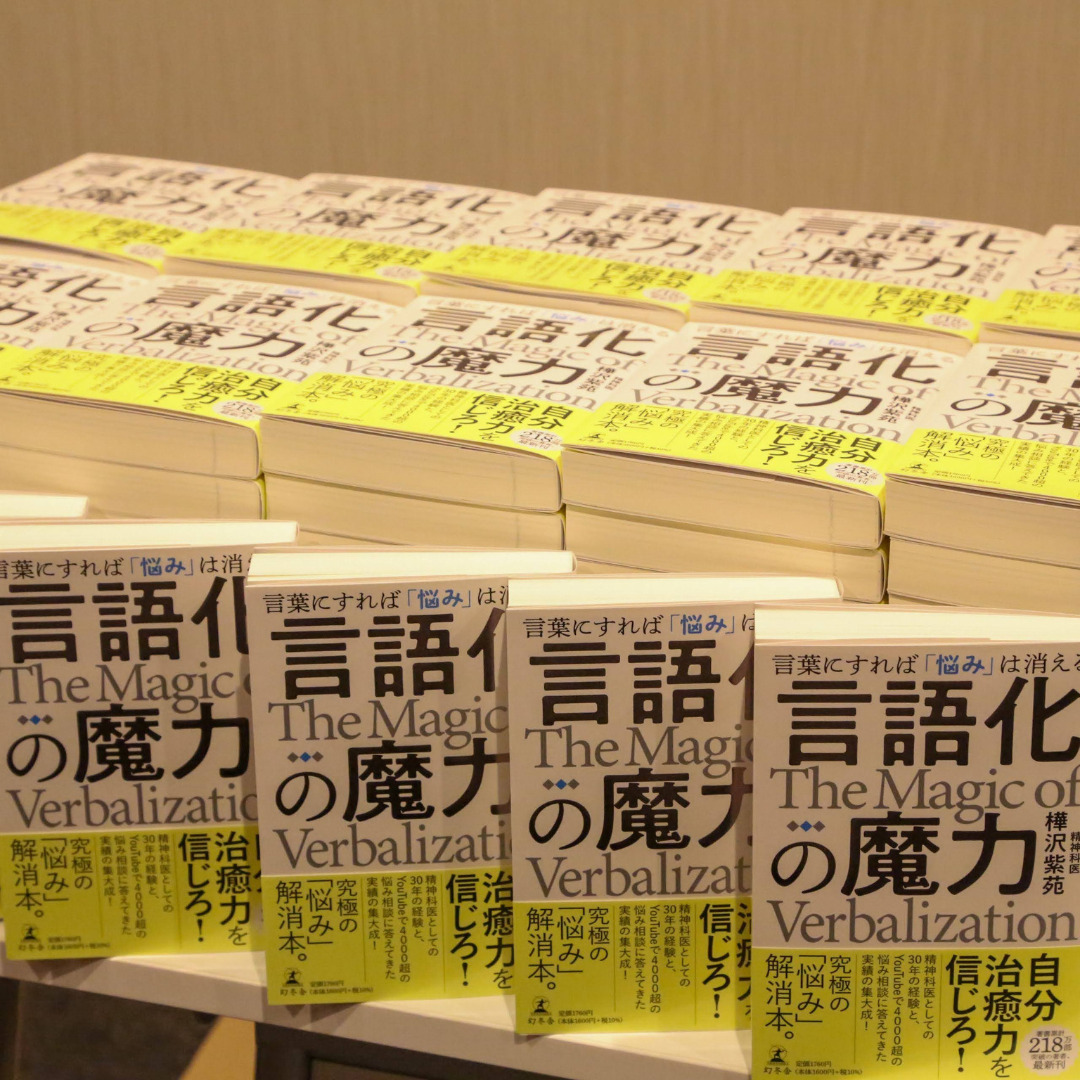
『言語化の魔力』を読んで
4,000件もの質問に答えてきた樺沢先生にしか書けない本がここに。
4,000の悩み・質問に答えてきた人って、他にいるんだろうか。
そして一体、どんな境地にたどり着くんだろうか。
「悩み」×「言語化」という特化した内容でありながら、
すべての生きとし生ける人に刺さるメッセージを届けられるのは、
4,000件もの質問に答えてきて、
「悩み」の真髄に到達した
精神科医・樺沢紫苑先生だからこそではないだろうか。
「悩み」とは、樺沢先生の定義によると、
「困難で苦しい問題に直面し、
『どうしよう?』『どうしたらいいんだ?』と前に進めず停滞し、
足踏みしている状態」とのこと。
世の中に「悩んでいる」人はどれくらいいるのか。
樺沢先生による独自アンケートの結果、
「悩みがある」と答えた人は75.9%で、
あとの24.1%は何かしら対処して、どんどん自己成長していることが分かった。
但しこの回答者は、樺沢先生のフォロワーが集まっている可能性が高く、
樺沢先生がさんざん「悩んだら検索、読書、相談、行動」(インプットして、アウトプットする)と
説いているのを聞いている層なわけだから、
悩んでも前進し続ける人の割合が世間より高めであることは容易に想像がつく。
実際に、日本人全体でみたら9割くらいの人が、
悩みに直面するたびに「ああどうしよう」と停滞しているのかもしれない。
私もこの本を読む前は、
悩みの尽きないタイプだと自負していたものの、
「あれ?悩んでるんじゃなくて、悩みの軽減、解消に向かっているってことか」と知った。
そもそも樺沢先生の教えに沿って自己成長の日々を送っていれば、
自分よりハードルの高い壁にぶち当たりまくるのは当然のことで。
充実しているだけなんだと気づくことが、もう既に大きな気づきであった。
それでもこの本は、そんな「悩み」の「解消」に向かっている人にも
充分学ぶところの多い本だった。
それは、悩みを解消するために、根本的な原因を取り除く必要はないということ。
やれることを、やれる範囲で積み上げていくことで、
「なんとかなる」というコントロール感があれば、ストレスは大幅に軽減されると。
この、「やれることを、やれる範囲でやっていく」ために、
悩みを「コントロール軸」「時間軸」「自分軸」の観点から分析して、
悩みの「視座転換」、「再設定」を行っていくことについて、
事細かに書かれている。
そこで「言語化」がどのように関わってくるのか。
人が同時に処理できる情報は3つまで。
悩みで苦しんで脳疲労を起こしている人のワーキングメモリは、
さらに小さくなっているという。
だから堂々巡りが起こりやすい。
そうならないために、「言語化」が必要。
頭のなかだけでモヤモヤ悩むのではなく、
それを「外化」するだけで、
脳にかかっていた負荷が軽くなる。
つまり、ワーキングメモリの空き容量が増える。
そうすれば、
先の「視座転換」、「再設定」もしやすくなる。
さらに「行動化」もしやすくなり、「悩み」の「解消」へとつながる。
…けど、そもそも重度の脳疲労に陥っていると、
その言語化すらできない。
から、たどり着くのは「心と身体を整える」ということ。
改めて、自分の生活習慣を見直そうと思った。
- 日の出よりだいぶ前に起床するので、朝起きてすぐ、リズミカルな運動をする。
- 5分休憩では、スマホを見ない。ぼーっとして、DMNを活発にさせる。
- 就寝時間を21時に固定する。
それから私は、地域経済の研究者という立場上、
自分の研究と地域の現実的な課題との乖離に
日々モヤついていた。
地域が抱える人口減少、少子高齢化、
交通インフラが弱いといった課題に、
地域経済学は本当に貢献しているのかと。
好き勝手に論文を書いてるだけじゃ、
もっともっと深刻な状況になってしまう。
この漠然とした問題意識。
悩みを「再設定」する質問を投げかけよう。
「本当に困っていることは?」
「その悩みが解決して満足できる?」
「その悩みが解消すると、幸せになれる?」
《働き手や買い手となる人も企業もさらに減って、
産業が衰退して、大学も潰れるのが心配》という自分の悩みと、
《地方に住んでいても、お金・働き口・資源・交通手段・情報・人脈を理由にせず、
誰もが自由に生きられる社会にしたい》というビジョンが出てきた。
悩みからビジョンっぽいものまで出てくるとは…
恐るべし悩みの「再設定」。
TO DOとしては…
・地域経済学の話を、分かりやすくかみ砕いて情報発信
・「すごい研究」ではなく、「現実的に有用な研究」を目指す
・セミナーやお茶会を企画して、地域の人との接点を増やす・地方在住を理由にせず、自由に生きている人の情報を集める
・経済が縮小しても生き生きとした地域の事例を集めてみる
・地域の課題を乗り越えてきた事例をストックする
・失敗事例の要因を学術的に紐解いてみる
・地域の課題を見出して、自分事として捉えて、自分の頭で考えて行動できる学生を育てる
・地方の人気な大学のマネできるポイントを探る
・大学教員以外の収入源を確保する
先日の出版記念講演会での特典でいただいた
「言語化の魔力」ノートには、
3ヵ月以内に達成できる具体的な目標として、
「地域経済学の解説を30本ブログに投稿する」と書こう。