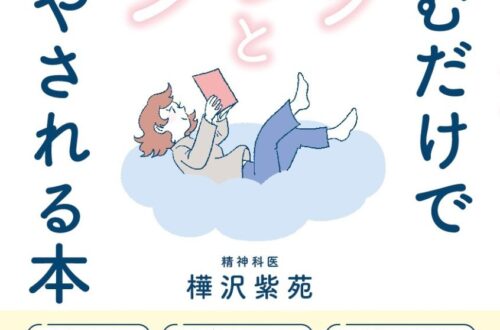『20代で得た知見』を読んで
意味のない本を読んでみた。
特に朝読むと、「しょーもな」「あっそう」となるような、
それでいて、夜読むと「わかりみ…」「クスクス」となるような本。
まさに秋の夜長にぴったり。
筆者が聞き集めた「私見」の数々。
でもそれらはすべて、筆者の心を動かした私見であり、
筆者自身の私見でもある。
そんな途方もなく意味のないエッセイを、
敢えてくそ忙しいときに読むという、意味のない贅沢。
ただ単に、専門書やビジネス書ばっかり読んでいる反動で、
文学的な表現に飢えていただけなのかもしれないけれど。
この本にある私見のなかでのお気に入りは…
第1位
創るということ
p.138より引用
第一稿は、誤字まみれである。直す。
第二稿は、誤字はないが独りよがりに見えてくる。直す。
第三稿は、もはや何が面白いか面白くないか分からない。人に読ます。直す。
第四稿は、ショートケーキで言うイチゴがそれでも足りない。イチゴを足す。
第五稿で、完成させる。つもりが結局、第九稿まで行く。
公開する。ぶっ叩かれる。泣く。チョコを食べる。
しかし一番忍耐を要するのは、第ゼロ稿を抱えて生きている時間です。
私の場合は論文だけど、ものを書く仕事の人なら、クスッとしてしまう話。
でも、さらっと「イチゴを足す」なんて書いてあるが、
それができなくて、私は結構、イチゴ不在で論文出しちゃうことが多い。
で、通っちゃう。
反省反省。
というかそもそも、自分が一度書いた論文を読み直し、書き直すのが、死ぬほど嫌い。
人の文章の校正は割と好きだけどね。
なんでだろう。
だから第九稿とか死んじゃう。
論文の場合は、そんなに直させてもらえないけど。
世間的に注目度も低い、というか読んでもらえるもんでもないので、
ぶっ叩かれるなんてこともそうそうないけども。
でも、先生諸氏、学生諸子から
突っつかれることはあるかな。
それで、自分をよしよしする時間をもつ。
第ゼロ稿も、ほんとその通りだ。
続いて第二位。
悪評についての一見解
pp.132-133より引用
(中略)
あなたがなにかを表現する時、物語る時、届けたい人ではない人にも届き、響かないであろう人にも届くでしょう。
そこから予想もしない返信が来るでしょう。
それは不運なことではあります。
しかし、それでもよいことなのです。
みながみな、よい、と言っているものはつまり、結局誰にも届いていないのです。
あなたはどうかご自身の仕事を続けてください。
淡々と、粛々と続けてください。
これを読んで私が思い当たるのは、大学での講義。
どんなに「よかれ」と思っても、受講生全員がそう感じるとは限らないわけで。
「お前は何しに大学に来たんだ」と言いたくなるような感想を
何も考えずぶつけてこられることもあるし、
今後もきっとそうなんだろう。
静かな絶望。
でも「勝手にやってれば。私はあなたじゃないのでどうとでも」という気も。
だからこそ、
「淡々と、粛々と」というのがいい。
とてもいい。
最後に第三位。
孤高の宝石
p.137より引用
誰もがやっていることは、誰もがやっているがゆえに、価値がありません。
稀少でなければ価値がない。
宝石も人間も、同じです。
ベストセラーなんか人に読ませておけばよろしい。
まだ誰も読んだことのない本にたくさん触れ、誰も気づいていないことを読み抜けばよい。
英語の資格や法律の資格のお勉強なんざ、暗記がお得意などなたかに任せて、いまだかつて誰も語ったことのないことを見て聴いて感じて、書いたり話したりする人の方が余程面白いでしょう。
群れる必要はない、というより、群れてもらっては困るのです。
ただ一人で生きているかのような顔をしていただきたい。
その方があなたを見つけやすい。
なにを書いても撮っても、あなただと分かる文体がある。
画角がある。
香りがある。
どうしようもない癖。
それをもろだしにしてもらった方が、あなたを好きになる人や、あなたが好きになる人が、あなたを見つけやすい。
もし孤独に未だ意味があるとすれば、この一点に於いてのみです。
はあ。
こんな風に生きてみたいものです。
今の私は、「なにを書いても撮っても、あなただと分かる文体がある」って、
ほんとかよと思ってしまうもの。
ありふれた感覚の持ち主に触れると、
なんともいえない空虚感に見舞われるものの、
誰もみたことのないものにはそうそう巡り合わない。
こんな宙ぶらりんな状態でもできることとしては。
共感されないものをそのまま貫いて、どこまでも追いかけてみよう。
この本の場合、
書いてあることを役に立てようというより、
なんでもないふとした瞬間に、
何度でもふらふらっと戻ってきたくなる感じ。